こんにちわ!はじめに・・・
その1でも申し上げましたが自然薯の栽培に関するお問い合わせが多くなっております。しかし自然薯は種芋の
入手、栽培方法は通常では難しく現在茨城県を中心にプロ専門分野が「種芋購入者」のみへ栽培方法は伝授して
います。
当園でもその方式でございましたが、家庭菜園レベルでの問い合わせ、又定年後の趣味として挑戦したい!・・・
などのお問い合わせが多く、この度の公開となりました。尚ホームページ内の横シート栽培(他地域でも類似あり)は当園独自の物でございますのでご了承の上ご参考にして下さい。
又、判らないことなどはメール等でご相談も受け付けております。
![]()
![]() 私達の本定植時期は通常5月下旬〜6月上旬ですが、地域差はあります。
私達の本定植時期は通常5月下旬〜6月上旬ですが、地域差はあります。
自然薯はすべて適期があります。芋の成長期である9月〜10月の環境作りが大切です。
下記のことを事前に準備しておくことで仕事の効率が上がります。
![]() 圃場の準備
圃場の準備
自然薯栽培で一番大切なことは、水はけの良い環境を作ることがまず第一に大切なことです。
又、野菜などの経歴がある場所では「センチュウ」などの対策も必要ですが基本的に自然薯は「弱酸性」が良いと
されています。(山の環境)・・・。石灰等は特には必要ありません。
水田地を利用する方が多いようですが、底を抜いた状態で無い場合は俳水路を深く、水はけをよくし圃場の外まで
水が抜けるようにしておきましょう。
地力はその土地の経歴、環境でも違いますが、堆肥は完熟を使用し出来る限り「有機質」の物を利用して下さい。
* 参考/ 堆肥施肥・・・1,000kg〜2,000kg(10aあたり)
![]() 資材の準備
資材の準備
私達の資材は、プロ、初心者でも共通の資材を使用することで低コストで出来る資材をご提供します。
1 専用シート(15cm〜17,5cm×130cm)/シートを種芋の数用意します。
その際、シートは紐等で縛り、U字の形状になるよう出来れば1月前には用意しておきましょう。*写真1参考
2 シート固定用クシ(約30cm×180cm)/シートを溝に埋める際、一時、両サイドから締め付ける為に
使用します。4個あると便利です。代品としては同サイズの板等でもかまいせん。 *写真1参考
3 畝作りの鍬(平)/溝を掘る際に使用します。量が多い場合はネギローター等を使用しても可能。
4 案内棒/定植する芋の位置の目印として使用します。
20cm〜30cm位の竹素材の物が適当ですが、割りばし等でも構いません。
 |
写真1 専用シートとクシです。(クシは新タイプに変更) シートは写真のように紐で締め付けて置く。 長期固定の方が形状がつき易くなります。 早めに仕上げておきましょう。 資材は特別頒布しております。 「自然薯栽培その1」最終ページ参考 |
5 山土、又は市販の赤玉土(細粒)、鹿沼土(細粒)
シート内には無機質で、水はけの良い土を入れます。有機質の土ではシート内に根が入り込む可能性があります
山の土を使用する場合は表面の土約10cm位をとり、その下の用土を使用しましょう。
当園では、赤玉土(細粒)を使用しています。)
以上、圃場と資材関係の準備はここまでです。
![]() 定植作業偏
定植作業偏
定植する段階での種芋は芽サイズで約5cmに伸びた頃が適していると考えますが一長一短があります。
発芽初期では、芽の位置が確定しません。中期では芽が欠けやすい。などがあります。
5cm位になりますと、欠けても新芽が出てきますが根が大きくなっていますので根を切らないように注意が必要です。
さあ!いよいよ定植しましょう!
でもその前にシート埋めは完了しておきしょう!・・・
数の多い方はシート埋めに時間がかかりますので厳守です。
定植までの草取りなど弊害がありますが、最低5日前には
完了しておきましょう。(定植前に降雨があれば理想です。)
![]()
以下写真を参考にして作業してください。(下記栽培方法は全体の8割程度をご案内しております。判らないことはお気軽にお問い合わせ下さい。
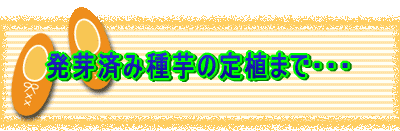
* 作業は2名以上ですると効率が上ります。 ![]() 傾斜をつける。
傾斜をつける。
 |
 |
 |
| ① 土壌消毒 当園では連作対策として土壌消毒をしています。 竹酢液の100倍を使用エコファーマー認定に付き農薬は殆ど使用しません。一般の方は必要ありせんが参考にして下さい。 |
②畝堀(1回目) 重要 一回目は浅く掘ります。(5cm位)この段階では、最初の堀始めを少し傾斜をとることが大切です。最初の傾斜がないとシートに傾斜がつきません。 必ず実行しましょう。 |
③畝堀(2回目) 一回目で掘りあげた場所を 広さ15cm、深さ25cm〜30cm位に仕上げます。 作業が多くなる方はネギローターなどを使用して作業を軽減しましょう。 最初の傾斜に注意! 畝巾/160cm〜180cm |
 |
 |
 |
| ④シート内へ用土を入れます。 シート内には山土か市販の用土を使用します。 用量はシートの3分の2位までですが、用土に余裕があれば多くしてもかまいません。 ここがポイント!・・・ シートの先端(定植する反対側の用土を少なくすることで成長した芋がシートから飛び出すことを防ぐことができます 写真は計量してシートに入れています |
⑤シートの埋め込み 先にクシ(代品)を刺しその間にシートを入れていきます。出来る限り圃場の土がシート内に入らないようにして下さい。 シートの間隔は20cm〜25cmですが間隔が多い程光合成も沢山になり環境は良くなります沢山芋を定植予定の場合は20cmくらいでも構いません。 当園ではクシに印をしておきます。写真 |
⑥絞込み1(新タイプのクシはこの作業の必要なし) クシの間に埋め込んだシートは写真のように両側から絞ります。⑦のように絞り、クシのすき間に両側の土を入れ固定します。 (シート内に土が入らないようにする) |
 |
 |
 |
| ⑦絞込み2 (新タイプはこの作業の必要はなし) 鉄棒などで地面にシッカリ刺し締めます ここがポイント!・・・ 締める意味は、芋が成長する家ですから広くなると曲がったり、長芋のように大きくなり過ぎます。クシの代用は板等でも可。 |
⑧シート埋めの繰り返し 写真のようにシート埋めの繰り返しです。畝の最終はシートのサイズに注意し圃場から出過ぎないようにしましょう。 芋を定植する株間(20cm〜25cm)の シートは広くしておきます。芋が降りる際にシート外に外れない対策です。写真⑨ |
⑨案内棒と用土入れ 用土に余裕がある場合は写真のようにシートの先端へいっぱいに入れると芋の根がシートに入るのを防ぐことが出来ます。 (無機質の為)案内棒は自分で芋を置く場所を確認する物です。定植はシートの先端2cm〜5cm位のシート中央です。 |
 |
 |
 |
| ⑩土を被せて終了です。 土はシート上に蒲鉾型に寄せておきます シート上部からから5cmくらいで余り多く寄せても芋がシート内に入らない場合があります 写真の畝巾は180cmです。光合成、風対策としても理想の間隔です。⑫で行う芋置きではシートの底から8cm〜10cmの位置に芋を置きますのでこで実施しておきますと楽に芋置きが出来ます |
⑪種芋の取り出し (重要) いよいよ種芋の定植です。 しかし初心者の方には注意が必要です この時期の芽と特に根は欠落し易いことです。 育苗箱からの取り出しは写真のように地面に砂を置き、箱を少し揺すりながらゆっくり砂を出し丁寧に芋を出していきましょう。根が張っていますので特に注意が必要です。 |
⑫種芋定植 案内棒で印をした位置に種芋を置いていきます。 ここで大切なことは芽と地面が垂直になるように置きましょう。(⑬参考) 芋の位置にこだわり、定植する芋の位置、横、縦は関係ありません。シートの底から8cm〜10cmが理想です。割り箸などに印をして地面から刺して計測していけば理想です。 ⑩で作業をしておきましょう。 |
 |
 |
 |
| ⑬種芋の位置 (重要) 芽と根は一体になっています。慎重に扱って下さい芽はいろいろな所から出ています。 ここがポイント!・・・ 写真のように芽、根が地面と垂直になるようにして置いていきましょう。又、乾燥に弱い芋ですから出来れば雨の後なを待ってからが理想です。 |
⑭土寄せ 定植後は乾燥が一番懸念されます。 必ず芋が見えていないか等確認して土寄せをして下さい。尚、この時点で元肥を兼ねて土寄せを蒲鉾型に行います。元肥は各土壌で差がありますが基本的には畝の盛り土と同時に全面散布をします。 参考/有機系成分6−8−4・・・15kg(100本) *センチュウ対策としては・・・ バイデード粒剤(摘用農薬)がありますので同時に散布しても構いません。 |
⑮支柱、ネット張り 自然薯の蔓は伸長にかかせません。 直管パイプ(19mm〜22mm)を使用し 約2m間隔で支柱をつけネットはキュウリネットを使用します。 (1,8m×18m)など・・・ 参考/支柱の高さ・・・1,8m 台風など強風が懸念される場所ではパイプの支えなど多めに使用し頑丈にしておきましょう。 |
 |
 |
 |
| ⑯敷き藁 敷きワラは梅雨明けが適しています。 早い時期に敷き藁をしますと根が浅く広がり夏の時期に充分な水分をとることが出来なくなります。その為にも根は深く誘導する為ワラ等は時期を遅らせます。乾燥防止、防草、防水にもなります。 代用品/マルチシート・市販のシート |
⑰追肥 追肥は8月中頃行いますが窒素の補給よりリン酸系を補給し芋の成長を助けます。 市販のサツマイモ専用が可です。 ご自分の圃場に合わせて下さい。 |
⑱地割れ 収穫期(11月〜12月)にこのような地割れがあれば芋は成長しています。・・・ 形状は?失敗も又勉強です! お楽しみに! |
むかごの収穫(食用)
9月頃に畝上にネットを敷き詰めると収穫は簡単ですが栽培規模にもよりますので
其々で実施して下さい。
むかごの着実はその年の天候等で大きく変化します。芋の成長とは関係ないようです
終り